台北の南には、数え切れないほどの文学にまつわる素敵な物語が隠されています。MRT古亭駅から出て同安街に足を踏み入れると、まるで時間を超えた不思議な旅に出るようです。そして、街のつき当たりに現れる紀州庵文学の森は、その文学的な雰囲気が醸し出されています。
1960年代末から1970年代にかけて、純文学出版社、爾雅出版社、洪範書店、遠流出版社などが次々と設立されました。また、文学の巨匠である余光中や王文興などもここを住居としていました。彼らはここで暮らし、ここで文章を書き、たくさんの南台北にまつわる話を書き留めました。余光中は廈門街113巷の先頭に住んでいて、彼の作品『日不落家(太陽の沈まない家)』では、出版社や他の作家との交流や生活を描いています。「路地の最後は同安街で、左に曲がって3~5分ぐらい歩くと『文学雑誌』の会社があります。本当に近所です。雑誌は毎月20日に発行されるので、その日になると私は劉宅に本を取りに行きます。そして、その日になると、夏濟安と吳魯芹は必ず劉宅に行ってマージャンをします。印刷工場が本を送ってくるのを待っている一面はありますが、新刊が出版される喜びも少しはあります。」
それなら、余光中は必ずと言っていいほど、廈門街113巷と同安街の交差点に静かに佇む古木「双吉榕」を頻繁に通り過ぎていたでしょう。双吉榕は一本のオオバアコウ です。周囲の出版社や書店の栄枯転変を見守り続けて、多くの作家の人生を見届けてきました。現在、ここを「雙吉榕公園」に変えて、その赤レンガには作家たちの言葉が刻まれています。それはまるで作家であり爾雅出版社の創設者である隱地が言ったように、「有限な生命の中で、無限な文学の木を植える」。遠くない爾雅出版社の壁にも、この言葉が刻まれています。目の前のこの双吉榕は、まるで無限の文学の木のように、多くの物語と記憶を抱えています。
この騒がしい都市の中で、木の下の一隅を選び、静かに座り、考えて、その南台北の文学の雰囲気を感じ、双吉榕がこの地域の台湾文学史を見つめる意味を味わいましょう。
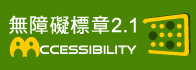
![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)
